特集
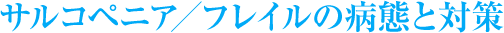
…8P
特集
サルコペニア/フレイルの病態と対策
超高齢社会を迎え、骨格筋萎縮や骨の脆弱性を背景としたサルコペニア・フレイルが問題になっています。とりわけ、糖尿病患者ではサルコペニア・フレイルが加速し、このことがさらなるエネルギー代謝障害を招く悪循環に陥るリスクがあります。
本特集では、超高齢社会で今後問題になってくる社会的フレイルという新しい概念、糖尿病とサルコペニア/フレイル病態のクロストーク、骨格筋量の評価法、食事・運動・薬物療法をテーマとして選び、それぞれのエキスパートの先生に解説いただきます。本特集をもとに、今後求められる糖尿病領域でのサルコペニア・フレイル対策に向けたチーム医療を議論したいですね。
社会的フレイルという超高齢社会の切り札
田中友規(東京大学)ほか…9P
糖尿病とサルコペニア/フレイルの病態
笹子敬洋(東京大学)ほか…13P
検査から考えるサルコペニアの診断―骨格筋量の評価―
高橋修(慶應義塾大学)ほか…136P
高齢者糖尿病のサルコペニア/フレイルに対する食事療法
山本恭子(虎の門病院)ほか…19P
糖尿病患者のサルコペニア/フレイルを運動で予防する
髙木大輔(健康科学大学)ほか…24P
サルコペニア/フレイルを抱える
高齢糖尿病患者に対する薬物療法
勝呂美香(北里大学病院)ほか…27P
新連載「糖尿病療養指導カードシステム」
糖尿病療養指導カードシステム概論
遅野井健(那珂記念クリニック)…31P
新連載「糖尿病療養指導カードシステム」
糖尿病療養指導カードシステム概論
糖尿病診療においては、疾病をよく理解した上で自己の病状を正しく認識し、個々の背景や価値観を踏まえて、生活習慣の是正や薬物介入に前向きになることが理想的です。異常高血糖の是正や教育目的での入院直後は良好であった血糖が次第に悪化して、再三の教育入院や栄養指導、さらには薬物療法を強化しても、十分な効果が得られない患者さんも少なくありません。このような治療困難例には、疾病や自己の病状の正しい理解を待たずにHbA1c の改善を急いだ結果、十分な受容がないままで治療が先行した可能性があります。このような事態の改善や防止には、受容の過程を十分に確認しながらの治療が必要です。また、指導者不足も多くの施設の課題となっています。そこで、タイムリーな指導介入および病状や患者背景の変化にも柔軟に対応し、指導者のスキルアップツールともなり得る糖尿病療養指導カードシステムを考案しました。
連載「地域医療の現場から」
やれる人がやる! これ以上悪化させない!
在宅糖尿病患者さんの生活に根差したオリジナルケア
~本人とともに、開業医・病院医・薬剤師・看護師・介護者・訪問介護士・
ケアマネジャー・デイサービス・友人知人・ご近所さんまで巻き込んで~
丸田恵子(訪問看護ステーションSTORY 学芸大学)…35P
連載「地域医療の現場から」
! これ以上悪化させない!
在宅糖尿病患者さんの生活に根差したオリジナルケア
~本人とともに、開業医・病院医・薬剤師・看護師・介護者・訪問介護士・
ケアマネジャー・デイサービス・友人知人・ご近所さんまで巻き込んで~
糖尿病患者さんの多くは入院治療より通院での治療を受けており、診断がついていない未治療の患者さんも含め、糖尿病患者さんのほとんどがいわゆる「在宅糖尿病患者さん」といってよいのではないでしょうか。特に糖尿病性腎症患者さんの割合は増加傾向にあり(図1)、慢性透析患者さんへの訪問看護の依頼は年々増えていると感じています。そして近年、高齢世帯・高齢独居・介護者の就労などによって、外来通院だけでは薬物治療・食事指導などの管理を適切に受けることや、継続することは困難な現状があります。実際、慢性透析患者さんの平均年齢は上昇しております(図2)。このような状況において訪問看護師の立場から、個別的でより生活に根差した在宅糖尿病患者さんの地域医療連携における課題について考えてみたいと思います。
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
療養指導のプロフェッショナリズム
野村英樹(金沢大学附属病院)…40P
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
療養指導のプロフェッショナリズム
総合診療科は、例えば消化器系や内分泌系のような臓器系統を特定せず、患者のあらゆる健康問題に対処することを特徴とする診療科である。総合診療医が働く場所は、救急外来、総合病棟、総合外来、診療所、訪問診療などさまざまである。そのような診療の場の違いや、地域社会や所属医療機関のニーズの違いによって果たす役割が異なるため、医療機関によって総合診療科が実際に行っている診療は大きく異なっている。しかしそのような中でも、多くの総合診療医が患者の行動変容を促すアプローチに取り組んでおり、糖尿病の療養指導を担う医療者との共通点は少なくないと思われる。また、診療以外の活動として医学教育に関わる総合診療医も多く、プロフェッショナリズムはその中で現在ホットなテーマとなっている。
連載⑯「糖尿病カンバセーション・マップTM」
地域に根差した糖尿病カンバセーション・マップ™
―ファシリテータートレーニングの醍醐味
増田千絵(市立旭川病院)…44P
連載⑯「糖尿病カンバセーション・マップTM」
地域に根差した糖尿病カンバセーション・マップ™
―ファシリテータートレーニングの醍醐味
2016 年度から糖尿病カンバセーション・マップ™(以下、マップ)の教育制度が新しくなり、これまでステップ1 とステップ2A に分け2 日間で行っていたファシリテータートレーニングが統合され、1 日で実施することになりました。地域密着型トレーニングと称し全国を5 つの地区に分け展開され、従来、ディレクター、トレーナーの体制で実施してきたファシリテータートレーニングも、エキスパートトレーナー、シニアトレーナー、トレーナー、トレーナーアシスタントの新体制で臨みます。新しくなった制度のもと、6 月には旭川で初めてのファシリテータートレーニングが実施されました。今回の開催にあたりシニアトレーナーとして準備、実施に携わり感じたことと、ファシリテーターとして実際に患者さんたちと関わってきた経験から、「地域性」に注目して、ファシリテータートレーニングの必要性と課題について考えたいと思います。
連載「糖尿病診療update」
ロコモティブシンドロームに対する運動の考え方
宮本俊朗(兵庫医療大学)…48P
連載「糖尿病診療update」
ロコモティブシンドロームに対する運動の考え方
我が国は超高齢社会となり、医療・介護保険などの高齢者を取り巻く問題が社会的な問題となっている。運動器の障害が要支援・要介護に直接的にも間接的にも関連することから、運動器の状態を良好な状態で維持していく必要がある。運動療法は糖尿病診療の柱を形成しているため、運動療法を実施できるような運動器の機能維持は糖尿病診療においても非常に重要である。運動機能を維持・改善することは運動を行える身体機能を備えることになり、様々な疾患予防の原点であると言えるかもしれない。
本稿では運動機能の維持・改善に着目し、日本整形外科学会から提唱されているロコモティブシンドロームの概念や評価を紹介し、ロコモティブシンドロームに対する運動の考え方について概説する。
糖尿病患者支援におけるチームビルディング
杉島訓子(元岡山県立大学)…52P
連載「糖尿病診療update」
糖尿病患者支援におけるチームビルディング
糖尿病をはじめとする慢性疾患を抱えた患者支援では、対象を生活者として捉え、対象者が自ら生活に沿った療養に取り組めるよう関わる事が求められる。近年、生活の多様化はますます進み、同時に医療の高度化、高齢化により療養支援の多様性は増大している。そのため対象者の生活に沿った支援を行うには、多角的に対象を捉え、様々な専門家がチームを組み、療養を支える事が必要である。また医療制度改革により地域包括医療が推進されており、今後は組織を超えたチームを確立する事が必要となる。
チーム医療を促進するためには多職種でチームを構築し、成長する事が求められるが、チーム医療は形骸化していないだろうか。チームビルディングの視点で機能するチームのあり方について考えていきたい。
連載「症例クイズ」
健康情報を信じすぎる2 型糖尿病患者への対応
伊藤ひかり(美濃市立美濃病院)…57P
高齢者への運動療法についての支援
竹田幸恵(石川県済生会金沢病院)…59P
インフォメーション
表2 第5 回日本糖尿病療養指導学術集会予告
日本糖尿病協会 療養グッズのご案内…1P
インスリン製剤およびGLP-1 受容体作動薬の取り違い防止を目的とした製剤区分マークについて…34P
2016 年度下期「糖尿病カンバセーション・マップ™」トレーニングのお知らせ/日本糖尿病学会 医療スタッフ優秀演題賞のお知らせ…61P
年間購読申込書…64P
表3 清野裕理事長、糖尿病療養指導 鈴木万平賞を受賞
次号予告/編集後記…62P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
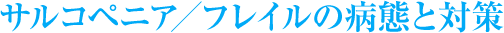 …8P
…8P


