2022年 Vol11. No.2(第48号)
2022年8月28日発行
特集
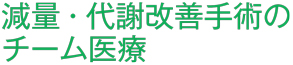
…6P
特集
減量・代謝改善手術のチーム医療
わが国では2014年に高度肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除術が保険適用となり、減量・代謝改善手術を施行する施設が着実に広がっています。その長期にわたる優れた効果の知見も蓄積しており、高度肥満症の治療の選択肢の1つとして期待されます。一方、高度肥満症の患者さんは睡眠呼吸障害や心不全、摂食障害など様々な心身の問題を合併する例も多く、減量・代謝改善手術においては、消化器外科、代謝・内分泌内科、心療内科、循環器内科、呼吸器内科、精神科、管理栄養士、看護師などの多診療科・多職種によるチーム医療が力を発揮します。その基本となる考え方は、一般の肥満や生活習慣病の診療に共通するものです。本特集を、減量・代謝改善手術におけるチーム医療の取り組みにお役立ていただければと考えます。
(秋田大学大学院医学系研究科 代謝・内分泌内科学講座 脇 裕典、福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 小林 邦久)
肥満症に対する外科的治療の現状と将来
太田 正之(大分大学グローカル感染症研究センター)…7P
高度肥満症診療における多職種チームアプローチ
齋木 厚人(東邦大学医療センター佐倉病院)…12P
減量・代謝改善手術患者の栄養管理の実際
栗原 美香(滋賀医科大学医学部附属病院)/山口 剛(滋賀医科大学)/卯木 智(近江八幡市立総合医療センター)…19P
減量・代謝改善手術患者における心理社会的評価の重要性
山崎 允宏(東京大学医学部附属病院)…26P
減量・代謝改善手術における病院連携と薬物治療
前田 和久(医療法人ロングウッド 前田クリニック)…30P
トピックス
肥満しやすさの遺伝的体質と肥満のスティグマ
脇 裕典(秋田大学)…36P
連載「地域発! 糖尿病療養指導士の活動報告」
「Moodle®」と「Zoom®」の活用でコロナに負けない研修会・認定試験の体制を構築 FROM 愛媛
中村 慶子(愛媛糖尿病療養指導士[ECDE]認定制度委員会事務局)…40P
連載「地域発! 糖尿病療養指導士の活動報告」
「Moodle®」と「Zoom®」の活用でコロナに負けない研修会・認定試験の体制を構築 FROM 愛媛
愛媛糖尿病療養指導士(ECDE)認定制度委員会は、2002年4月に、ECDEの第1回認定試験を実施しました。それから約20年、毎年の認定試験に加えて、5年ごとに実施している認定更新の審査も4回目を迎え、2022年には認定者総数は405名になりました。
委員会は愛媛の糖尿病治療に必要な「正しい知識を提供します」「チーム医療を推進します」を基本理念に、長年、地域での研究会の開催を継続し、活動の場を広げ、研修の質を高めてきました。2020-2021年には新型コロナウイルスの感染拡大によって研修会や認定試験の実施が困難になり、何よりもECDEとしての患者支援が難しくなりました。しかし、苦難の中で、学習システムやウェブ会議システムを活用することでコロナ禍でも研修会・認定試験を実施できる体制を構築。2021年2月にはeラーニング研修会を開催し、2022年4月には新しい試験方法で2年ぶりに認定試験を実施することができました。ECDE認定制度委員会の誕生から20年、組織の概要や活動について紹介します。
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」 漢方内科
「糖尿病と漢方治療」
岡田 直己(かがやき糖尿病内分泌クリニック新神戸)…49P
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」 漢方内科
「糖尿病と漢方治療」
漢方治療は明治維新に西洋医学が重視され一時衰退したものの、その後もニーズが高く、1976 年には医療用漢方製剤が保険薬価基準収載に採用されました。また、2001年には医学教育モデル・コアカリキュラムに漢方治療が採用され、2002 年には薬学教育モデル・コアカリキュラムにも採用されています。
漢方医学とは漢(中国)から伝来した医学という意味ですが、現在は伝統的な中国の医学を基に日本で発展した伝統医学に現代医学的研究を統合したものとなります。治療手段には漢方薬や鍼灸が用いられます。紀元5世紀頃大陸から漢方医学が伝わったといわれており、奈良県明日香村の飛鳥京庭園跡から脳卒中に用いられる続命湯という処方が書かれた木簡が出土し、日本最古の処方箋として話題になりました。このことから7世紀には既に当時最新の中国の医学が伝わっていたことがわかります。また奈良時代の正倉院には漢方薬の原料となる薬物が納められていますので、漢方治療の歴史は相当古いと言えます。もともとは宮廷や貴族が治療の対象でしたが、庶民にまで広まり始めたのは鎌倉時代頃からといわれています。
本稿では、漢方薬の種類や診断、糖尿病治療における役割や代表的な漢方薬について概説します。
症例クイズ
インスリンの打ち間違いが疑われる独居患者
佐々木 修二(ささき内科・糖尿病クリニック)…55P
連載「糖尿病診療update」
SGLT2阻害薬の新たな作用
慢性心不全と慢性腎臓病(CKD)への応用
秋山 滋男(東京薬科大学)…58P
連載「糖尿病診療update」
SGLT2阻害薬の新たな作用
慢性心不全と慢性腎臓病(CKD)への応用
日本では、2014年4月にSGLT2(Sodium-glucose co-transporter-2)阻害薬として初めてイプラグリフロジン(商品名スーグラ錠)が上市されました。発売当初は、糖尿病性ケトアシドーシスや脱水、尿路・性器感染症などの有害事象の発症の懸念から慎重に投与されることが多く、処方頻度も低い薬剤でした。その後、SGLT2阻害薬は2型糖尿病や1型糖尿病のほか、慢性心不全、慢性腎臓病においても新たに効能・効果を取得し注目を集めています。本稿では、SGLT2阻害薬の新たな作用である慢性心不全および慢性腎臓病への効能・効果についてご紹介します。
インフォメーション
日本糖尿病協会 医療の現場から、糖尿病にまつわることばを見直そう…表2
日本糖尿病協会 高齢者向けアプリのご案内…2P
日本糖尿病協会 糖尿病患者さんの食事療法を支える冊子…38P
日本糖尿病協会 血糖自己測定器 保守点検のお願い…57P
日本糖尿病協会 療養グッズのご案内…表3
次号予告/編集後記/購読確認票…64P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
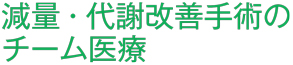 …6P
…6P



