Last Update:2022年10月7日
2022年 Vol11. No.1(第47号)
2022年5月28日発行
特集
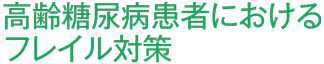
…8P
特集
高齢糖尿病患者におけるフレイル対策
高齢の糖尿病患者さんの治療においては、血糖管理だけではなく、要介護状態の前段階であるフレイルを予防すること、また、フレイル状態からの脱却を目指すことが非常に重要です。糖尿病はフレイルを来しやすい疾患であり、その要因としては身体活動の低下や低栄養、高血糖・低血糖、合併症などが挙げられます。フレイル対策としては、運動や食事の管理がまず頭に浮かびますが、この他にも様々な専門分野において対策が取られており、近年多くの知見が蓄積されています。本特集では、フレイルの病態について基本的な知識を学ぶとともに、運動・食事による対策、オーラルフレイル・嚥下機能障害や自律神経障害に対する対策、フレイル対策における臨床検査の役割について、様々な分野から解説していただきます。本特集が高齢社会における糖尿病治療の一助になれば幸いです。
(四條畷学園大学 リハビリテーション学部 本田寛人)
フレイルの病態
松本 彩加、吉村 芳弘(熊本リハビリテーション病院)…9P
運動によるフレイル対策
山田 実(筑波大学)…15P
食事によるフレイル対策
福田 也寸子(武庫川女子大学)…21P
オーラルフレイル・嚥下機能障害とその対策
渡邊 裕(北海道大学)…27P
自律神経障害からみたフレイルとそのケア
青木 美智子(千葉中央メディカルセンター)…32P
フレイルにおける臨床検査の役割と展望
~病棟検査技師の可能性~
神前 雅彦(兵庫医科大学ささやま医療センター)…38P
連載「地域発! 糖尿病療養指導士の活動報告」
コロナ禍でもステイホームでスキルアップ!
多彩な取り組みを進めています FROM 東京
菅原 正弘(医療法人社団弘健会 菅原医院)…44P
連載「地域発! 糖尿病療養指導士の活動報告」
コロナ禍でもステイホームでスキルアップ!
多彩な取り組みを進めています FROM 東京
東京糖尿病療養指導士認定機構は2017年3月に設立され、今年で5年目を迎えました。当機構では、東京都とその近郊にお住まいか勤務施設のある方を対象に、東京糖尿病療養指導士(以下、東京CDE)と、東京糖尿病療養支援士(以下、東京CDS)の2つの資格の研修と認定を行っています。
現在の認定者数は、東京CDEが930名、東京CDSが147名の合計1077名です。2022年4月1日より約300名が新たに認定される予定です。受験者用講習会や資格更新のための研修会はeラーニングにより開催し、認定試験はパソコンで出題、解答するCBT(Computer BasedTesting)システムにより実施するなど、コロナ禍でも安心して研修や認定を進められる取り組みを行っています。
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」 形成外科
足と歩行と生活を守るフットケアにするために
石井 義輝(小倉第一病院)…50P
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」 形成外科
足と歩行と生活を守るフットケアにするために
糖尿病性足病変は非外傷性下肢切断の代表的な原因疾患として知られています。さらに、糖尿病患者さんは足病変再発リスクも非常に高いため、複数回・複数箇所の切断になることも少なくありません。切断により足を失うと、歩行能力が失われるだけでなく、他臓器の合併症発生リスクも上昇します。今後さらなる高齢化が予想される我が国において、足を失う患者さんが増加すると、ご本人の生活のみならず社会全体にも大きな影響を与えることが危惧されます。
重症の足病変を減らしていくためには、他の疾患と同じように発生予防、早期発見・治療、そして長期フォローをいかに適切に行うかが重要になってきます。フットケアは、全ての段階において非常に重要な役割を果たすものと考えますが、日常臨床の場においては残念ながら十分行えていないように思われます。本稿では、重症病変の治療を行ってきた形成外科医の立場から、フットケアがよりよいものとなるよう、日常のケアで注意してもらいたいことについて述べたいと思います。
連載「糖尿病診療update」
糖尿病患者さんの運動療法に役立つ慢性疼痛への理解
中楚 友一朗、井上 雅之、牛田 享宏(愛知医科大学)…56P
連載「糖尿病診療update」
糖尿病患者さんの運動療法に役立つ慢性疼痛への理解
痛みは多くの人が経験し、様々な疾患によって現れる愁訴です。元来、急性疼痛には生体防御反応という役割がありますが、慢性疼痛ではそのような警告としての意味はなくなり、生活動作や仕事などにも影響を与え、生活の質を低下させます。海外の疫学調査によると、糖尿病患者さんは一般的な同年代の人に比べて、慢性疼痛を有する割合は高いといわれています。その背景には、糖尿病患者さんの糖代謝異常に付随する筋骨格系の変化や神経系の変化があると考えられています。また、糖尿病の治療において運動・身体活動は重要ですが、慢性疼痛がその妨げになることがあります。そのため、糖尿病患者さんの運動指導に関わる医療者も、慢性疼痛についての知識を持つことは重要です。本稿では、糖尿病に特徴的な慢性疼痛問題を概説します。
インフォメーション
第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 開催のお知らせ…表2
第9回 日本糖尿病協会年次学術集会 プログラム…1P
ウォーキングアプリ「そとでる」のご案内…2P
血糖自己測定器 保守点検のお願い…4P
療養グッズのご案内…63P
鈴木万平賞 推薦募集のお知らせ…表3
次号予告/編集後記/購読確認票…64P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
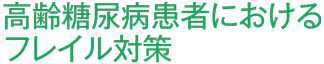 …8P
…8P



