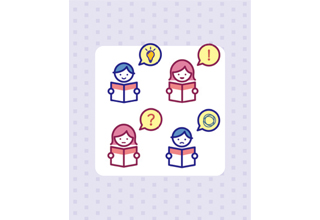Last Update:2020年12月8日
2020年 Vol9. No.2(第40号)
2020年8月28日発行
特集
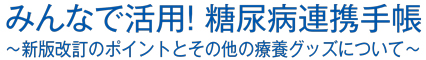
…6P
特集
みんなで活用! 糖尿病連携手帳~新版改訂のポイントとその他の療養グッズについて~
糖尿病連携手帳が新版に改訂されたことにお気づきでしょうか?
糖尿病患者さんの療養において“連携の輪”は非常に大きく広がっています。病院とかかりつけ医の連携だけでなく、内科・眼科・歯科の連携、かかりつけ薬剤師、ケアマネジャー、そして行政も参加した大きな連携が構築され、糖尿病患者さんの人生をサポートする時代になりました。質の高い糖尿病療養環境の実現には、連携内の情報共有が重要です。また、患者さんが置き去りでは連携する意味がありません。
糖尿病連携手帳は、患者さんを中心に“連携の輪”の情報共有ツールとして使用されることを念頭において、第4版に進化しました。今回の特集を読みながら糖尿病連携手帳を見ていただくことで、手帳に対する理解と愛着が深まれば幸いです。
(大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 柴田大河)
新・糖尿病連携手帳 改訂のポイント
下野 大(二田哲博クリニック)…7P
糖尿病連携手帳の地域連携への活用
西岡 恵子/坂本 則子/赤司 朋之(社会医療法人シマダ 嶋田病院)…12P
糖尿病性腎症重症化予防プログラムと糖尿病連携手帳の活用
矢部 大介/加藤 丈博/堀川 幸男(岐阜大学)…20P
We are 糖尿病療養グッズ編集委員会
野見山 崇(国際医療福祉大学市川病院)…26P
連載「地域医療の現場から」
One TeamでTryする糖尿病診療~糖尿病クリニックの新規開業から病診連携~
橋本 健一(はしもと内科 糖尿病・内分泌クリニック)…32P
連載「地域医療の現場から」
One TeamでTryする糖尿病診療~糖尿病クリニックの新規開業から病診連携~
当院は令和元年10月10日に、内科・小児科を標榜する地域のかかりつけ医であるとともに糖尿病・内分泌疾患の専門クリニックとして、岐阜県大垣市で開業しました。
厚生労働省の平成26年国民健康・栄養調査によると、糖尿病が強く疑われる人の割合は、前期高齢者(65~74歳)で18.3%、後期高齢者(75歳以上)では19.7%と報告されています。また、Japan Diabetes Clinical Data Management Study Group(JDDM)では平成28年の糖尿病患者の平均年齢は66.33歳とされ、高齢者糖尿病の増加が報告されています。
大垣市は人口約16万人で岐阜県第2の都市ですが、人口に占める65歳以上の割合である高齢化率は平成23年で22.5%でしたが、平成26年には25.0%に上昇し、今後も上昇が予想されています。当院の開院から令和2年3月までに受診された2型糖尿病患者さんの中での前期高齢者は19.2%、後期高齢者は9.6%で、2型糖尿病患者の平均年齢は57.5±12.6歳(31~86歳)であり、比較的若い糖尿病患者さんも多い環境ですが、幅広い年齢層を対象に対応しているクリニックです。
「糖尿病診療update」
インスリン注入器用A型注射針の適正使用について
~適切な注射部位と注射方法を指導できていますか~
虎石 顕一(さくら病院)…40P
「糖尿病診療update」
インスリン注入器用A型注射針の適正使用について
~適切な注射部位と注射方法を指導できていますか~
インスリン注射導入の際、医療従事者は患者さんに対しインスリン治療が適正に実施できるよう、施設ごとに様々な工夫を凝らした自己注射指導を実施しています。しかし、患者さんのインスリン自己注射は徐々に自己流になっていき、ある時、想定外の打ち方をしていることに医療側が気付き、再指導が必要となるケースを多々経験します。
近年、ペン型注入器用注射針でJIS T3226-2に準拠したA型専用注射針(以下、A型針)は、患者さんの穿刺時の恐怖心や痛みといった否定的な感情を軽減する観点から、より細く短い製品が上市されるようになってきました。しかし、細く短い注射針を用いたインスリン自己注射は、筋肉内注射のリスクが低下する半面、その短さゆえに皮内注射となるリスクが指摘されています。
今回、インスリン適正使用の観点から皮下注射の方法を再確認し、筋注リスクの回避方法について紹介します。また、A型針の製品開発の歴史も併せて紹介します。
運動療法とセルフ・エフィカシー
濱島 一樹(北里クリニック)…46P
「糖尿病診療update」
運動療法とセルフ・エフィカシー
セルフ・エフィカシーは、行動を起こす前に個人が感じる「遂行可能感」、つまり「できる自信」であると表現できます。セルフ・エフィカシーは、糖尿病療養行動の実施と関連があり、セルフ・エフィカシーを高めることで、療養行動や自己管理を円滑に進め、血糖コントロールの改善に導くことができると考えられています。運動療法の実施に関しても、セルフ・エフィカシーが高い患者さんは、運動実施率が高いという報告や、血糖コントロールが良好であったという報告がなされています。
セルフ・エフィカシーは、自然発生するわけではなく、いくつかの情報源により左右されるとされています。つまり糖尿病治療に携わる医療従事者は、セルフ・エフィカシーの情報源を基に、患者さんのセルフ・エフィカシーの向上に対しての介入方法を考察・実施することで、長期にわたる療養行動から離脱させない役割を果たすべきだと考えます。
症例クイズ
肥満妊娠糖尿病における食事療法
不破 千香子(社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院)…57P
血液透析中の糖尿病腎症患者
長井 梓苑(KKR高松病院)…59P
日常生活活動の中で考える指導ポイント
西田 昌平(公立豊岡病院)…61P
インフォメーション
糖尿病とともに生きる人へ…表2
お家でエクササイズ動画のご案内…37P
新型コロナウイルス感染症に負けない毎日を過ごすために…38P
腎機能(eGFR)チェックツールを公開…52P
インスリン注入器使用時の「空打ち」について…54P
DM Ensemble 年間購読申込書…63P
次号予告/編集後記/購読確認票…64P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
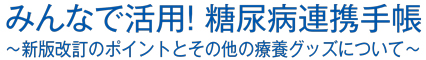 …6P
…6P