2016年 Vol5. No.2(第21号)
2016年8月30日発行
特集
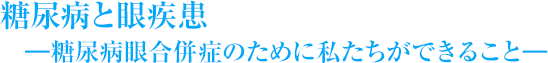
…8P
特集
小児糖尿病サマーキャンプ半世紀
―現在・過去・未来―
我が国の小児糖尿病サマーキャンプは、1963年に丸山博医師により始められました。それから半世紀の歴史を重ね、今では全国51カ所で開催されるほど広まりました。1型糖尿病は、小児人口10万人に対して1.4~2.2人と極めて少なく、子どもがインスリン注射をしながら成長していく過程には多くの困難が予測され、子どもだけではなく家族にとっても、医学的、心理・社会的支援の場が必要です。
本稿では、小児糖尿病サマーキャンプに関わる医師、看護師、栄養士の方々のみならず、当事者の方々にもご執筆いただきました。これまで果たしてきた役割、成果、現状、そして未来に向けて、共に小児サマーキャンプについて考えていきたいと願っています。
(日本糖尿病協会インスリンケアサポート委員会・横浜創英大学 中村慶子)( 山梨県立大学 米田昭子)

小児糖尿病サマーキャンプの創生と変遷
―小児糖尿病サマーキャンプの50 年を振り返り概観する―
武田倬(鳥取県立中央病院)…9P
小児糖尿病サマーキャンプを初めて開催してからの苦しみの道、初めてのことばかり
丸山博(小児慢性疾患療育会/わかば会)…12P
糖尿病サマーキャンプの意義と評価
―糖尿病サマーキャンプに期待すること、評価できること―
中村慶子(横浜創英大学)…15P
私達のサマーキャンプ紹介
北海道つぼみの会サマーキャンプ 太田和幸(北海道つぼみの会)
沖縄県小児糖尿病サマーキャンプ「ハッピーサマークラブ」 難波豊隆 ほか(琉球大学)
山形小児糖尿病サマーキャンプ 大通尚(山形大学)
新潟小児糖尿病キャンプ 小川洋平(ペガサスの会/新潟大学)…19P
糖尿病サマーキャンプの参加経験を語る
生喜葵(京都滋賀サマーキャンプ)…21P
サマーキャンプの支援について
発達障害のある小児1 型糖尿病児を糖尿病サマーキャンプで支援する
藤本正伸(鳥取大学)…22P
食育の大切な機会としての糖尿病サマーキャンプ
― 1 型糖尿病を持つ子どもの食事指導の基本を見直す―
福島芳子(谷口内科/武居小児科)…25P
チーム医療としての糖尿病サマーキャンプ
―小児科から内科への移行―
桶田俊光(赤坂おけだ糖尿病内科)…26P
インスリンメンターがサマーキャンプへの支援を担う
―役割・期待されること―
山本真吾 坂本辰蔵(日本糖尿病協会)…27P
連載「地域医療の現場から」
糖尿病と共に生きる人々を支える看護を目指して
―山梨県の地域の現状と未来―
志村好子(山梨大学)…29P
連載「地域医療の現場から」
糖尿病と共に生きる人々を支える看護を目指して
―山梨県の地域の現状と未来―
筆者は、山梨県第1号の糖尿病看護認定看護師となり、パイオニアとしての苦労もありながら、フットケア外来開設や県内で糖尿病看護専門・認定看護師会設立を行い、患者さんたちのQOLの向上・糖尿病看護の質の向上のため、現在も奮闘しています。しかし、糖尿病患者さんに携わる多くの方々と同じように、思うように患者さんの行動変容が見られず、燃え尽きそうになった日々もありました。そのような経験や患者さんとの関わりが原動力となり、今日の自分があると思っています。
そして、糖尿病看護のやりがいは、医師や薬の力だけではなく、患者さんを全人的に捉え、日々の生活を支援する看護の力が遺憾なく発揮できる点にあると思っています。また「やまびこの会」のサマーキャンプにも参画し、毎年参加者たちからパワーをもらっています。日々の患者さんたちとの関わりの中で、自身も学び、成長している事を実感しながら看護しています。
連載⑮「糖尿病カンバセーション・マップTM」
糖尿病カンバセーション・マップ™ 新教育制度
原島伸一(京都大学)…35P
連載⑮「糖尿病カンバセーション・マップTM」
糖尿病カンバセーション・マップ™ 新教育制度
日本糖尿病協会(日糖協)が糖尿病カンバセーション・マップ™(以下、マップ)普及事業を開始して6年が経ちました。この間、多くの方々にマップが知られるようになり、また、ファシリテーターの資格を取得された方も1000名を超えました。
日糖協では、マップのさらなる発展のためにマップトレーニング制度を見直し、より多くの方々にファシリテーターの資格を取得していただけるように改革しました。ファシリテータートレーニングは1日で実施され、また、ファシリテーターのスキルアップのためのフォローアップトレーニングも実施します。フォローアップトレーニングでは、新しいマップも紹介します。さらに、ファシリテータートレーニングを担当するトレーナーへのステップアップも可能となります。
マップは、グループダイナミックスを利用した療養支援のあり方を変える画期的な糖尿病学習教材です。糖尿病療養支援に携わる多くの医療従事者の方が、これまで以上にマップのトレーニングを受講していただき、糖尿病患者さんとともに歩むことを期待しています。
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
糖尿病は口腔外科診療の脅威となるか
天笠光雄 渡部隆夫(日高病院)…40P
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
糖尿病は口腔外科診療の脅威となるか
2012年の国民健康・栄養調査では糖尿病治療中、または検査で糖尿病が疑われる者(HbA1c6.1%以上)は950万人(7.6%)、糖尿病の可能性が否定できない者(HbA1c5.6%以上6.1%以下)は約1100万人(8.6%)、合わせて約2050万人(16.1%)と推定されており、2002年に比べ、1.2~1.3倍増加している1)。近年は、糖尿病と歯周病の関連が注目され、歯科医療者はもちろん、国民の関心も大いに高まっている。
なお、糖尿病と歯周病については、この連載の第1回(『DM Ensemble』Vol.1No.3)に報告されているので、歯周病以外の口腔外科疾患と糖尿病との関連について述べる。
連載「糖尿病診療update」
2型糖尿病患者における生活習慣トータルマネージメント
―福岡県糖尿病患者データベース研究( Fukuoka Diabetes Registry )より―
大隈俊明 ほか(九州大学)…47P
連載「糖尿病診療update」
2型糖尿病患者における生活習慣トータルマネージメント
―福岡県糖尿病患者データベース研究( Fukuoka Diabetes Registry )より―
糖尿病患者の世界的な増加は、その合併症の増加により、深刻な社会問題となっており、糖尿病合併症の発症、進展予防への対策が急務とされている。血糖値をはじめとした合併症の危険因子の管理は、新薬が続々と開発されているものの薬物療法のみでは困難で、病態の根底にある生活習慣の是正が不可欠である。増加の一途を辿る医療費、患者の経済的負担を鑑みても、非薬物療法である生活習慣是正の重要性は増している。
生活習慣には人種差、民族差があるため、我が国での有効な対策を行うには、日本人を対象とした研究による知見が必要である。しかし、我が国の糖尿病患者の大規模集団を対象に、生活習慣が合併症の危険因子や発症に及ぼす影響について調査した研究は稀である。そこで、我々が行っている糖尿病患者を対象とした前向きゲノムコホート研究である、福岡県糖尿病患者データベース研究(Fukuoka Diabetes Registry:FDR )から得られた知見を中心に、生活習慣に関する最近の研究成果を紹介する。
実践に活かすアクションリサーチ
―糖尿病患者教育に関するアクションリサーチ―
高樽由美(高知県立大学)…52P
連載「糖尿病診療update」
実践に活かすアクションリサーチ
―糖尿病患者教育に関するアクションリサーチ―
看護師のマンパワー不足や患者背景の複雑さに伴う教育的関わりの難しさなど様々な問題を抱えながら、日々糖尿病患者の教育やケアを実施している医療現場において、いかに状況の改善を行っていくかが課題となっている。このような現状を改善するためには、看護の質と向上を目指した研究が必要であり、その点で研究と実践との間を橋渡しするアクションリサーチは重要な研究手法であると考える。アクションリサーチの紹介と、日々の看護実践の中から生じた「どのように糖尿病患者の教育を改善すればよいのか」という疑問への取り組みとして、アクションリサーチ法を方法論として用いた研究について紹介する。
連載「症例クイズ」
糖尿病患者のシックデイ対策
伊藤勇(美濃市立美濃病院)…57P
インスリンボールを見逃さないで
長嶋美里(信州上田医療センター)…59P
インフォメーション
第4回日本糖尿病療養指導学術集会開催報告…1P
日本糖尿病協会 若手研究者助成応募要項…61P
年間購読申込書…64P
表3 日本糖尿病協会 清野裕理事長 ADA 受賞報告
次号予告/編集後記…62P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
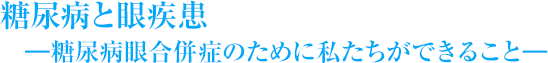 …8P
…8P 小児糖尿病サマーキャンプの創生と変遷
小児糖尿病サマーキャンプの創生と変遷


