2016年 Vol5. No.1(第20号)
2016年5月30日発行
特集
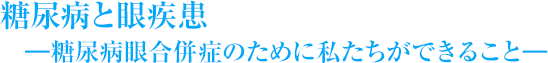
…8P
特集
糖尿病と眼疾患
―糖尿病眼合併症のために私たちができること―
糖尿病眼合併症による視力障害は日常生活への影響が直接的であり、患者の生活の質に直結します。従って、糖尿病患者の療養指導に携わるメディカルスタッフが相互理解を深めることで、糖尿病眼合併症の眼科医による診療に適切に届けることが期待されます。
診療や指導の現場では「私たちができること」を1 人ひとりが主体的に考える姿勢が求められます。この特集には、誰がどのようなタイミングで何をするべきかについて、自らの力で考えるためのヒントが散りばめられています。糖尿病眼合併症の治療と指導のタイムラインを意識してお読みいただき、皆さんの診療や指導の更なるスキルアップのきっかけを提供できれば幸甚です。
(川崎市立川崎病院 糖尿病内科 津村和大)
良好な眼科・内科連携のために ―当院の取り組みと問題点―
林哲範(北里大学)…9P
眼科受診を継続するために必要な「認識」と「力」を生み出す支援
伊波早苗(草津総合病院)…13P
糖尿病眼合併症の患者ケア ―事例から看看連携を振り返る―
新良啓子(横浜労災病院)…16P
眼科病棟看護師が取り組む糖尿病合併症予防
大倉瑞代(千葉大学医学部附属病院)…20P
視覚障害者に対する薬物療法・血糖自己測定を適切かつ安全に実施するために
虎石顕一(宗像医師会病院)…23P

視覚障害が生じた際の安全な運動方法について
舟見敬成(総合南東北病院)…26P
糖尿病カンバセーション・マップTM特別座談会
糖尿病カンバセーション・マップ™ 6年の軌跡と未来
矢部大介(司会/関西電力医学研究所)
清野裕(関西電力病院) 東山弘子(関西電力医学研究所) 大部正代(中村学園大学)
原島伸一(京都大学) 中尾友美(聖マリア学院大学)…32P
糖尿病カンバセーション・マップTM特別座談会
糖尿病カンバセーション・マップ™ 6年の軌跡と未来
糖尿病治療は長期に及びます。そのため、患者さんは日々の血糖管理だけでなく、食生活への気遣いや経済的な負担増など、様々な悩みを抱えることが少なくなく、患者さんを支える家族もまた、それらの悩みを共有しています。そうした糖尿病治療をめぐる課題の多様性を踏まえ、国際糖尿病連合(IDF:InternationalDiabetes Federation)は、糖尿病患者さんやその家族がグループでの話し合いを通して糖尿病への理解を深め、糖尿病治療に前向きに取り組めるようにするサポートツールとして、糖尿病カンバセーション・マップTM(以下、カンバセーション・マップ、またはマップ)を開発しました。日本糖尿病協会(日糖協)は、このカンバセーション・マップの普及活動をIDFの要請により開始し、マップを効果的に用いることのできるファシリテーターのトレーニングを2010年に開始しました。この取り組みが開始されて6年が経過した現在、マップは糖尿病診療の現場にどの程度浸透しているのか、その過程でマップはどのように評価されているのかなど、普及活動に尽力されている先生方にお話しいただきました。
連載「地域医療の現場から」
医療連携で糖尿病診療のレベルアップ
傍島裕司(大垣市民病院)…39P
連載「地域医療の現場から」
医療連携で糖尿病診療のレベルアップ
大垣市民病院( http://www.ogaki-mh.jp/ )は、2市9町(人口約39万人)の岐阜県西濃医療圏で唯一の地域中核病院です。糖尿病・腎臓内科の常勤医師は8名で、4名が糖尿病領域を担当しています。西濃医療圏は慢性的な医師不足に加え、糖尿病専門医の数も全国平均の60%以下と少なく、糖尿病診療にとっては恵まれた環境とはいえません。以前は当院の外来に多くの糖尿病患者が集中し、日常業務に支障が出ることもありました。地域医療のサポートがなくては糖尿病診療が立ち行かないという状況下で、2001年から全国に先駆け地域連携型診療が始まりました。15年にわたる地域連携は、紆余曲折があるものでしたが、保健行政との連携にも発展し、今日の地域糖尿病診療レベルの向上に寄与したのではないかと感じています。2013年度に院内にCDEJを中心とした糖尿病診療チームが発足し、院内の糖尿病診療の充実のみならず、地域患者会との連携、地域の糖尿病医療スタッフのための研修や連携を行えるようになりました。地域連携の経緯や今後の課題についてご紹介します。
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
呼吸器内科から見た糖尿病患者の禁煙指導
安部崇(大垣市民病院)…44P
連載「糖尿病をめぐる診療科リレー」
呼吸器内科から見た糖尿病患者の禁煙指導
禁煙指導は2006年から保険適用となり、喫煙習慣は「ニコチン依存症」という疾患であるという認識のもとに、喫煙関連疾患の有無にかかわらず希望者には標準的な禁煙指導ができるようになっている。一方、2008年からは特定健診が開始され、「メタボリックシンドローム」が広く世間一般に知られることとなり、生活習慣を改善することによって心血管障害をはじめとする重大な疾患の発症riskを減らすことができるという考え方が徐々に浸透しつつある。この2つの治療は、どちらも同様に生活習慣の改善によって将来のriskを低減することを目標としているが、これまで連携して治療介入にあたることは少なかったように思われる。そこで、2013年4月に厚生労働省健康局から公表された「標準的な健診・保健指導プログラム(改訂版)1)」では、「禁煙支援を行う重要性は高い」と記載され、タバコに関する専門的な知識をもって適切な禁煙指導をすることを求めている。
喫煙と糖尿病は、ともに3大死因をはじめとする重篤な疾患を引き起こす最も重要なrisk factorである。糖尿病患者が喫煙を続けていれば、危険因子の重複によってriskがより高くなるのはいうまでもない。今回、禁煙指導をする呼吸器内科医の立場から、糖尿病診療における禁煙指導について考えてみたい。
連載「糖尿病診療update」
糖尿病 ―歯科の関わりと医科歯科連携
安藤雄一(国立保健医療科学院)…50P
連載「糖尿病診療update」
糖尿病 ―歯科の関わりと医科歯科連携
糖尿病は、歯周病と双方向の関連を有しているといわれる。加えて、歯周病が進むと食物摂取に影響が出て食生活の面から糖尿病に悪影響を与えること、糖尿病のリスクと歯科疾患(歯周病、う蝕)のリスクが共通していることから、糖尿病に対する歯科の関わり方は多様である。糖尿病であることが明らかな対象層に対するアプローチでは、病院において健康教育や歯科衛生士等による専門的ケアを行う事例が増えてきているようであるし、糖尿病ハイリスク者の重症化予防対策に歯科が関与する事例も現れてきた。一方、歯科医院には地域住民の約半数が1年に1回程度受診することから、歯科患者から糖尿病のスクリーニングを行って医科受診につなげるアプローチも行われるようになってきた。しかしながら、歯科医院では受診患者の糖尿病の状況を把握しづらいという問題があり、この解決に向けたトライアルも行われている。本稿では、糖尿病と歯科との関わりを述べ、糖尿病に関する医科歯科連携について概説する。
糖尿病患者への継続的栄養指導
―継続的な栄養指導から見えてくる今後の課題
米田昌代 ほか(牧病院)…54P
連載「糖尿病診療update」
糖尿病患者への継続的栄養指導
―継続的な栄養指導から見えてくる今後の課題
世界中で糖尿病患者数は急速に増大しており、我が国でも厚生労働省の「2013年国民健康・栄養調査報告」では国民の6人に1人以上が糖尿病かその予備群であることが明らかになっている。しかし、20歳以上で糖尿病が強く疑われる人のうち、男性・女性ともに約35%の人は受診をしていない、または、通院を中断している。これらの事から、糖尿病患者の治療は、患者と医師の2者間で行う対面的治療法では限界があることが明らかになってきている。そこで、取り組みとして、入院や外来での多職種からの指導や、糖尿病友の会を活用した啓発活動などがある。本稿では、管理栄養士による継続的な栄養指導によってHbA1c値が改善したことを示し、その内容について分析した結果を紹介する。
連載「症例クイズ」
運動を頑張り過ぎてしまう人への運動指導
村藤卓秀(岡山済生会総合病院)…59P
夜勤がある人へのインスリン療法の導入
髙見千恵(木沢記念病院)…61P
インフォメーション
日本糖尿病協会 療養指導カードシステム 講習会スタート!…28P
第4回日本糖尿病療養指導学術集会のお知らせ…31P
2016年度糖尿病カンバセーション・マップ ファシリテータートレーニング…58P
次号予告/編集後記…64P
定期購読
DM Ensemble 定期購読申込フォーム
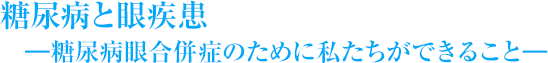 …8P
…8P
 視覚障害が生じた際の安全な運動方法について
視覚障害が生じた際の安全な運動方法について



